モンゴル通信 モンゴル高原から送るEメール
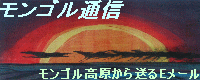
ギルモア著「モンゴル人の友となりて」
モンゴル通信 モンゴル高原から送るEメール
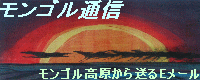
ギルモア著「モンゴル人の友となりて」
第29章 モンゴルの説話
仏教に身を捧げて修行するものを励ましたいときには、モンゴル人はよく次のような物語をするが、これは言うまでもなく、数ある仏教伝説の中の一つを通俗的に焼き直したものである。
一人のラマが山に籠もって、ひたすら瞑想と祈祷と研鑽とに身を捧げた。仏陀の悟りを開きたいとの願いから熱心に修行したが、三年経っても求道の験はなかった。
今は疲労困憊し、赤貧洗うが如くなったラマは、ついに山住まいを捨て、俗人になろうと下山してきた。その道すがら、険しい崖の下にさしかかると、一人の男が、一本の頭髪をもって崖を挽き切ろうとしているのを見た。
「何をやろうとしているのですか?」
とラマが尋ねた。
「 私はこの崖を切り開こうとしているのです。」
と答える。
「何ですって?」とラマは聞き返す。
「この髪の毛でですか? そんなことができるものじゃない。」
男は答えて
「出来ますとも。出来ないことがあるものですか。飽くまで耐え忍べば、きっとこの髪の毛で、この崖を切り開くことが出来るでしょう。」
これを聞いたラマは大いに考えさせられ、思案しながらそこを離れた。
「あの男は不平も言わずにここに座り込んで、一筋の髪の毛で崖を切り開くなどと言う、まるで見込みのなさそうな仕事を続けている。私も落胆してはいけない。私は悟りを開きたいと三年間修行をし、開き切れずに失望した。
しかし、この男と比べれば、三年くらいは取るに足りない。失望したことがむしろ恥ずかしい。そうだ、もう一度帰ろう。そしてもう三年修行しよう。」
山に帰ったラマは、また三年間難業苦行を積み重ねたが、やはり悟りは得られなかった。
再び気も挫けて、もう修行は止めて環俗しようと、山を下りて、ふと丘を通りかかると、一人の男が大釜を据え付けて、岩から折々滴る水を受けているのに出会った。
「何をしているのですか?」
とラマは問う。
「釜に水を満たしているのですよ。」とその男、驚いたラマは、
「何ですって? こんな大きな容れ物に、たまたま落ちてきたり、落ちてこなかったりする水滴を一杯にしようというのですか?」
「それは手間はかかりますよ。でもいつかは一杯になりましょう。」
これを聞いたラマは感心してまた考え込んだ。
「私は六年間仏陀のお姿を拝みたいと修行して、まだ拝めないので失望した。しかし、この男が、この釜一杯になるまで根気良く待つことが出来るなら、私も六年間の無駄骨を折ったからといって挫けてはならない。そうだ、帰ってもう三年修行を続けよう。」
ラマは山に帰った。また三年経った。それでも仏陀のお姿は拝めなかった。
精も根も尽き果てた彼は、もう何もする気もなくなって、俗界に入ろうと山を下ってきた。
彼がちょうど麓まで来たところ、見るも哀れな一匹の雌犬が居て、毛は抜け落ち、赤膚は蛆に悩まされている。
ラマは立ち上がって、どうしたものかと思案した。もしも蛆を犬から取れば蛆は死んでしまうであろうし、そのまま蛆のたかるに任せて置けば、犬の方が死ぬであろう。
この板挟みに陥った彼は、とうとう自分の太腿の肉を剥ぎ取って、半分を蛆に与え、半分を犬にやろうと思いついた。
あわやこれを実行しようとしたとき、頭上に後光が射したと思うと、幻影が現れた。これこそ弥勒菩薩のお姿であった!
犬はと見れば、その姿はない。その幻であったのである。
弥勒菩薩はラマに、何者か、また何をする者かとお尋ねになった。
ラマは、お姿を拝みたいと熱心に願って、九年間修行を続けたが、望みは叶わず、心は常に闇であった、と愚痴を零した。
思いがけなくもお姿を衣の様子が変った。
「愚かな者よ、仏は常に汝の傍に居り、一寸たりとも離れはしなかった。見よ、汝の息吹が、仏の衣をいかに汚したかを!」
こう弥勒菩薩が宣った時、忽ちにしてこのラマは純然として大悟徹底した。
二、 善王と悪王
モンゴル人は善根を勧め、悪業を戒める時に、よく次の話をする。
ある所に一人の良い王様が居て、貧しいものや遍歴の僧に慈悲深かったのみならず、王は何人にも物惜しみせず与えたので、ついに無一物に近くなった。
王には唯一の息子があったが、死期が近づくや、臨終の床に呼び寄せ、汝の父を手本にし、そのやった通りにせよ、と言い残した。王は持てる限りのものは、持たざるものに与えるよう心掛けていたのだ。
父王が死んで息子が王国を継いだ。その受け継いだ遺産というべきものは、貧乏だけであった。
その上に父王の教訓を守ったので、赤貧ますます洗うがごとき有様となった。彼の父王の言い付けは明らかであった。
「もし一尺の布でも持っていて、持たぬ者に逢ったら、その半分を与えよ。もし二椀の稗を持っていて、持っていない者に逢ったら、その一椀を与えよ。」
その教訓を守ったので、若き王は、ついに十文を残すのみになった。物乞いの僧が訪れたのでその中から五文を与えた。今は五文を残すのみとなった王は、その僧と運命を共にしたいと申し出た。ラマは快諾して、二人は揃って旅立った。
魔法使いの力を疑う者を説き伏せようとする時には、モンゴル人は次のような話をする。
ある名高い魔法使いの法力が問題となって議論された時、一人の向こう見ずな若い男が、魔法使いは威力を持っていて、他の者なら騙すことができるかもしれぬが、自分だけは騙されないと言い放った。
この高言を聞いた魔法使いは、立派な鞍を黒毛の駿馬に置いて、その若者の住家に乗って来た。
話はすぐに、よく言われる魔法使いの力ということに落ちて、若者は一度それを試して見たいといった。
魔法使いは、結構だが、少し心配があるので、それを解決しておきたいと語った。
それは、今シナ人が彼の家に来ていて、前に借りた十両の借金を返せなければ、てこでも動きそうもなく、といって今金の算段もつかず、結局シナ人は黒毛の駿馬を抵当に曳いて行こうとしているが、三十両もする馬を十両の抵当にやりたくはないので、二十両でこの若者に買ってもらいたいと思ってきたという。
ちょうどこの話のとき、若者の細君は、魔法使いと夫と自分にお茶を入れかけていたが、その間に馬を一目見て来ようと夫は外へ出かけていった。
外へ来て馬を一目見た瞬間に若者は、正気を失ってしまった。
それからどこをどう歩いたか分からないが、やがて彼は無人島を彷徨っていた。
あちこちと歩き回った揚句、海辺に近い山の麓に辿り着いた。
するとそこに一軒の小屋が立っていて、行ってみると一人の婦人が住まっている。婦人は何者とも明かさなかったが、彼も自分のことは何も言えなかった。
ともかく、彼は一両日その家に滞在することとした。
やがて暇を告げる時が来たが、何となく去りがたい心持であったし、また行く先もないので、とうとう彼は婦人に結婚を申し込んだ。
二人は夫婦になった。そして、お互いの生活が少しはましなものになった。
妻は山へ行って薪を取り、水を汲み、家事に精を出し、夫は狩をして暮らしを支える。
そうするうちに子供が生まれたので、両親の喜びは一方でなかった。彼らは言った。
「ああ、とうとう私たちは三人になった。もう恐れることはない。」
それから二年過ぎて、また一人生まれた。
「ああ、われわれは四人になった。もう安心して暮らしてゆける。」
と彼らは話し合った。こうして六年も経ったある日のこと、父は仕留めた鹿を背負って帰ってくると、一方母親も薪の束を持って家に差しかかるところであった。
ちょうどその時、下の子が海の方に這って行って、あなやと見るまにまっ逆さまに海に落ちた。
弟を助けようとした上の子もまた後から落ちて溺れた。
狂気のようになって駆けつけた母は、二人の子供を救おうとして力及ばず、彼女も落ち込んでしまった。
背中の鹿を放り出した父親は息を切らして現場に急いだが、なにもかもついに遅かった。
もはや手の施しようもない。いまや彼は再び孤独になった。
それから一、二ヶ月は実に惨めな生活を送った。鹿肉を得ようとすれば薪に困るし、薪を取りに行けば食うものがなくなる。
やがて彼はまた意識を失って自分がどこにいるのか分からなくなってしまった。
しかし、だんだん自分のゲルに似たものが見え出し、その前に馬も繋いであったので、おやと思う間に正気づいてきた。
よく見れば、妻が声を荒げて、お茶が冷めてしまいますよと、揺すっていた。
やがてことの真相が彼に分かった。魔法にかかっていたのである。
そして、注いだ一椀の茶が冷え切らないうちに、六年にあまる生活の、喜びと悲しみを嘗め尽くしたのであった。
四、画工と建具師
隣人に仕掛ける悪巧みを防ごうとするときには、モンゴル人は次のような話をして、人を呪わば穴二つの教えを示そうとする。
ある王様が位に即いた時のこと、人民の中に日ごろ仲の悪い画工と建具師がおり、ある日画工が若い新王の御前に出て申し上げた。
「父君は転生遊ばしまして、私に御使者を賜りました。参上致しますと、先王様はそれはそれは御幸せにお暮らしでいらっしゃいまして、私にこのお手紙をお言い付け遊ばしたのでございます。」
手紙というのは、息子である若い王に宛てたもので、次のような文面であった。
「私は今天国にいるので誠に幸福である。ところで私は寺を建立しようと思っていたのだが、ついては息子よ、お前の町から建具師の「広悦」を私の許へ寄越してもらいたい。お前の治める王国が栄えてゆくのを私は嬉しく思う。お前の善政を布こうとする努力を、私はここから助けてあげよう。」
若い王はこの手紙を読んで大いに喜び、さっそく建具師を呼び寄せて、言われた。
「父上は天国にお生まれ変わりなさったので、寺を建立したいとの思し召しから、お前お迎えをおつかわしになったのだ。」
王はこういいながら例の手紙を彼に手渡された。建具師は手紙を読んで内心思った。
「そんな馬鹿な話があるはずがない。あの画工の奴はいつも悪巧みをするのだから。」
こう考えながら王にお尋ねした。
「ではいったいどんな風にして天国に参ったらよろしゅうございましょう?」
王は再び画工に下問された。すると画工の答えるには、
「建具師を道具と一緒に真ん中に据えて、その周囲に薪を積み重ね、油を注ぐのでございます。それから太鼓・ばち・笛・胡弓などの音に合わせて、薪に火をつけます。すると建具師は煙馬に乗って昇天することができます。さよう父王様が仰せられました。」
建具師が返事申し上げた。
「参りますにつきましては私にも多少の用意がございます。七日の内に旅支度を調えますでございましょう。」
それから彼は家に戻って、自分の妻に画工の悪巧みを一部始終物語った。そして、その姦計を逃れるため、自分の家から焼かれる場所まで地下道を掘り抜き、最後の所は石で蓋をし、その上をまた砂で覆った。
ちょうど七日目に、王様は建具師を父王の所に送ろうとして、人民から一籠の薪と、一瓶の油を徴収した。
これをことごとく積み上げ、建具師を道具とともに真ん中に据え、やがて火を放った。
太鼓が響く、撥が鳴る、笛が響いて、やがて煙が轟々と立ち込めるや、建具師は地下道に抜け出し、道具を背負って、まんまと家に帰って来た。画工は天にも届く煙を見やりながら、
「あそこの建具師が昇天してゆく。」
と絶叫した。見物人たちは随喜の涙をこぼし、
「建具師は昇天した。」
と語りながら散って行った。
建具師は一月の間家に潜み、その間に毎日牛乳の風呂を使って、自分の体を白くした。ちょうど一月位経ってから、彼は絹の衣を着けて王の御前に伺候し、前王の手紙を奉呈した。手紙にはこんな文句が書いてある。
「お前が王国を忠実に治めていることを嘉みす。建具師の「広悦」はここに寺を建ててくれたから、その骨折りをよく労ってくれるよう。寺は今度は外装をしなければならぬから、画工「久悦」を、建具師の時と同じ方法で遣わしてくれ。」
「お前が天国に参って、父上はお喜び遊ばしたか?」
王がそう問われたので、建具師は実際に天国に行ってきたかのように、いろいろお話をした。
若き王はご機嫌斜めならず、建具師にご褒美をたくさん賜った上、あらためて画工を迎えさせられた。
画工は建具師が色白になり、絹衣を纏うているのを見て、死なぬのを驚いたばかりか、ほんとうに天国に行ってきたのだと思い込んでしまった。自分の計画通りほんとうに彼の敵が煙馬に乗って昇天したと思ったので、画工は七日したら自分も参りましょうと快諾した。
その日、その時刻が来た。
画工は塗料と筆を持って、油のかかった薪の中央に据えられ、火がつけられた。煙が上がった。
煙はたちまち彼を包んでしまった。熱さ苦しさにのた打ち回り、声を限りにわめいたが、太鼓・撥・笛・胡弓の音に打ち消され、ついに画工は真っ黒に焼け焦げてしまった。
、
(EOF)