モンゴル通信 モンゴル高原から送るEメール
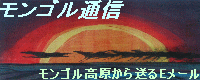
ギルモア著「モンゴル人の友となりて」
モンゴル通信 モンゴル高原から送るEメール
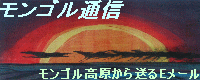
ギルモア著「モンゴル人の友となりて」
第二章 モンゴル語点描話
北京を出発する前に、私は「北京・キャフタ間道路図」を贈られた。
この地図は、北京・張家口間は役に立ったが、それより先は無用の長物であった。
なぜなら、張家口からキャフタまでは何本も道があるのに、その地図には一本だけしか載っていなくて、われわれはこれと違う道を行ったからである。
しかし、地図の欄外に、少しだけれどもモンゴル語の単語と熟語が記してあり、研究心の強い旅行者が砂漠の土着民と話をする場合の助けになるように工夫されていた。
これが私の最初のモンゴル語会話書として役に立った。
砂漠旅行のためのモンゴル人と駱駝が見つかるまで、約二週間張家口に逗留している間に、私は、ちょうど、お世話になっていたアメリカ人宣教師の教師をしていたモンゴル人に教えを受けた。
地図とモンゴル人教師、この二つの助けの他に、シュミットのモンゴル語文法書もかなり熟読した。張家口出発までには、中国語を介して、モンゴル人教師に「私はモンゴル語を話せません。
今モンゴル語を習っています」というモンゴル語の文句を教えてもらい、これによってこれから出会うモンゴル人との絆をつくり、日常生活の共通の事柄や行為を示す言葉を話させることができるだろうと考えた。そのため、いつも鉛筆と小さなノートを携帯して、こういった言葉を書き留める用意をしていた。
言葉も物も、このように貧弱な用意だけで砂漠に入り、見つかるだけの言葉を片っ端から書き取ろうとした。
私はまもなくモンゴル人教師を思い出す破目になった。だんだん言葉が判るようになると、あのモンゴル人教師が教えてくれて、私が挨拶するモンゴル人の大部分に得々として繰り返していた文句は、「今、モンゴル語を習っています」という表現ではなく、ただ知っているだけの雑多なモンゴル語を並べていただけのことだと気づいた。
地図の欄外の言葉の中には役に立ったものもあり、モンゴル人が私の発音のせいで判らなかったものもあった。これもモンゴル語を英語の綴りで表現することが難しいことであるから驚くには当たらない。中には記してある章句が遠方の種族の慣用語であって、我々が旅行しているモンゴルの土地では普通には使われないものもあった。
シベリアに到着して最初の一ヶ月は、ブリヤート語を話す区域で過ごした。私は、とあるロシア人の家に寄寓し、教師の助けを借りたり、ノートと鉛筆を持って民衆の間に入って行って、言葉の書き抜きに努めた。この場合に必ずしも同じ成果は得られなかった。多数の有用な語句を書き抜いた日もあり、そうした成果の見られない日もあった。私はいつも、シベリアに住むモンゴル族ーブリヤート人のテントを訪ねるていたが、多くは鄭重に迎えてくれたが、時には疑惑の目で見られる場合もあった。
雪の日、あるゲルを訪れ、調子よく主の青年から多くの言葉を聞きだしていると、三、四人の人相の悪い男が入ってきて、主の青年に何事か言って、私に詰問しようとした。それがどんな印象を主のブリヤート青年に与えたものか、闖入者に妨げられた仕事を続けようとすると、「知らない」という以外の返事をしなくなった。
何か行き違いのあったことは確かで、これ以上手の施しようがないので、私はそのゲルから立ち去った。私は自分の行動が注目されていることは知っていた。数日して、主の青年が帰ってきて、数人のブリアート人が得たいの知れない妙な人物と知り合いになって、これを捕まえて地方長官に差し出そうとしたという耳よりの話を聞かせてくれた。彼らは実行に移さなかったが、青年の様子と私の疑惑を述べて地方長官に通知した。地方長官は、私がこの地に居残っていることに気づいたので、通知したブリヤート人の興奮を鎮めることができた。
その後は、言葉の収集に疑惑を招いたこともなく、半ページにわたる語句をしとめて、大猟を自慢する狩猟家のように誇らかに帰宅する日もあった。
このように一ヶ月を過ごしてキャフタに戻り、寄宿先に閉じこもって、主としてスタリブラスとスワン両氏が ブルヤート語に翻訳した聖書の読解に力を注ぎながら、モンゴル語の研究に従った。
しかし、適当なモンゴル語の教師を見つけることは難しく、ようやく見つけた教師は無能力で、しかも一日の中で一番都合の悪い時間に、疲れ果てて半ば居眠りしているような状態でしかやってこない。ひたすら研鑽に努めたけれども、私のモンゴル語は思うように進歩しなかった。
ついに、我慢しきれなくなった。というのは、ある晩、友人がたまたま私が招いたラマと話をしているのを聞いて、もし、彼が私ほど長くモンゴル語を研究していたら、もっとうまく話せるだろうと語ったのである。
前から激しい勉強にもかかわらず、明らかな進歩が見られずに飽き足りなく思っていたところ、この友人の言葉は冗談半分で悪意のあるものではなかったけれども、最後の止めを刺された思い(背負い切れぬ荷物を積んだ駱駝の背に最後の藁一本を積んだ)であった。
翌朝、犬よけに重い散歩杖を手にして、国境を越えてモンゴル領のキャフタに行き、歩いて二時間かかって、前から親しくしていたラマのゲルを訪ねた。
ゲルに近づくとラマの声が聞こえてきて、私が入ると一言「座れ」と言って、手まねで場所を示しただけで、相変わらず読経を続けていた。座ると、十分か十五分間は私の存在を無視していたが、まもなく読経が終わり、たった今私が入ってきたかのように挨拶するのであった。
お茶を沸かし、しばらく雑談してから、私の訪問の目的、つまり彼のゲルに同居して、彼を先生としてモンゴル語を習いたいと述べた。彼はすごく乗り気であったが、ただゲルがあまりに貧弱なので私が凍えはしないか、またモンゴル風の食べ物しかご馳走できないから私の口に合わないのではと心配した。
いつから始めるかという彼の質問に答えて「今すぐに」と言うと、快く承諾してくれたので、早速もうモンゴルゲルの同居人になったように感じた。
翌朝、寝具などを取りに、彼はキャフタの私の住居まで同行してきたが、道々、我々は条件について相談をまとめた。彼は一日に一人一シリングと少しばかりの代金で、食わして住まわして、かつ教えてくれることを承諾した。
それ以来、私は一週間をロシア人とモンゴル人の下宿に割り振って、三日、四日あるいは五日をゲルで暮らし、残りを文明の裡に過ごすことにした。
ゲルについては、一から十まで、驚くほど私の要求に適った。所有者のラマは二百マイルばかり郷里を離れてきているので、我々は彼のよけいな家族に煩わされることがない。
また、彼はここを仮の住まいとしているので、犬もおらず、私は自由に出入りできた。彼は富裕なので、いつも威勢のよい火を絶やさなかったが、これは到底貧乏人のゲルでは許されない贅沢であった。
彼は職掌柄、いつも三人の下僕を身辺に置くことを必要とし、また、このような地位にある人間として上等の茶ー砂漠の大きな魅力ーを手元から話しがたい。したがって、ゲルの中に二、三人のモンゴル人が閑談していないときはほとんどなかった。
この後者ーモンゴル人によって傍若無人に語られる会話は、まさに私の欲するところで、私は鉛筆とノートを手にして座り、捉まえ得た語句を書き留める例であった。
ゲルを出入りする場合に交わされる感動詞や挨拶の文句、隣人や訪問客に対して、またこれについて行われる批評、蓄群の監視や炊事や火のつぎ方について召使に下す指示、何れもありのままの斬新さと純粋さをもってこれを補足して手帳に書き写した昼や夕方の人のない時に、書き留めたところを繰り返し繰り返し熟読するのである。
このような語学の学習方法によって、まもなく私は自分が理解し、また教師の説明してくれる以上に話ができるようになった。
熟語の分解もできず、単語の組み立てを分析することもできず、自分の話すことの意味にいたってはもっと理解できていなかったが、どんな場合に、どんな風にこれを使うかが判り、もっとも普通に用いられる言葉を学んだのである。
こうして、本で学ぶ時間を少なくして、やがて相当の進歩をしたと自分でも認めることができるようになった。